「宅建主任者」から「宅建取引士」へ
「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に名称変更するなどの宅建業法改正が、国会で可決され後の2015年の4月1日から施行となりました。 一見すると、わざわざ「…主任者」から「…士」に変更するだけなのに大袈裟なことをと思いますが、実はなかなか大変な手間と年月が掛かっております。 法案等によりますと・・・暴力団に関係した人は、そうでなくなった日から5年間経過すること、暴力団関係者がその事業活動を支配する場合はダメ。
「宅地建物取引士」を含めた宅建従事者の倫理規定・コンプライアンス意識と、重事項説明の内容が年々増加するなど、取引に関する法律や関連制度が多様化するため宅地建物取引士の責任は益々重くなっています。
確かに、かつての重事項説明書は一棟売マンションでも、A3用紙一枚だけなんてのも見たことがありますが、今では考えられないことです。
その為、専門的知識の習得などに更なる研修制度が実施されています。 我々当事者としては、これらが有料化されたり、新たな団体に加入したりするのを恐れている次第です。なぜなら、今まで新しい制度や法律の整備がなされると、それが新たな天下り先に繋がる口実なんてことだったら由々しき問題だと思うからです。 「宅地建物取引士」は、その不動産会社の営業関係者の「5人に1人必要」というのが絶対数必要ですが、以前からくすぶっていた「3人に1人必要」にしようというのは、当分の間はなさそうだというのです。理由は、十分な教育を受けた「宅地建物取引士」がいて、その他の従業員もボトムアップするからその必要はないということらしいが・・・正直いって、その意味はよくわかりませんなぁ~
いわゆる“士業”といえば、弁護士、不動産鑑定士、司法書士など「士」と呼ばれる専門性の高い国家資格の俗称ですが、最近では、マンション管理士やファイナンシャルプランニング技能士などの新参ものもありますが、「宅地建物取引士」も専門性の高い国家資格だと言うのであれば、不動産の営業に関わる人は全員その資格を持つことが望ましいのじゃないでしょうか。
「宅地建物取引士の記名押印」
売買や賃貸借の契約をする時には、その契約前に宅建業法第35条に定める重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印及び同第37条に定める書面(契約書等)への記名押印は、「宅地建物取引士」が行う必要がありますが、不動産業者でも意外と勘違いしていることがあります。 まず、宅建業者が売主の場合や複数の仲介業者が存在している取引の場合も、すべての宅建業者が宅地建物取引士の記名押印をしなければならないということ。
| 宅地建物取引業法 第37条1項(書面の交付)
(注)1項は「売買又は交換」2項は「宅地又は建物の貸借」でほぼ同じような内容です。 |
| 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 |
| ■取引の当事者の氏名(法人にあつては、その名称)・住所
■物件の住所・所在、地番・種類、構造 ■取引金額やその支払の時期及び方法 ■引渡しの時期・移転登記の申請の時期 ■契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 ■損害賠償額や違約金の内容 ■天災その他不可抗力による損害の負担と内容 ■当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任 ■公租公課の負担と内容・・・・・・等が主たる事項です。 |
それに、宅建業法第37条では、いちいち細かくは書いていませんが、売主が業者の場合、仲介業者が記名押印しているから売主自らの記名押印を不要だとはしていません。 また、仲介業者が複数の場合、根付業者が代表して記名押印すれば、その他の中間業者は仲介手数料を受け取るために領収書さえ持ってくればイイというものではありません。
昔ほどではありませんが、今でも意外といいラフな場合も多いようですが。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
事業用不動産の売却・購入・買い替えなどのご相談はお気軽にご連絡お願い申し上げます。また、いろいろな身近なご相談も受け賜りますので、お電話やメールでも結構ですので、お待ち申し上げます。
≪一棟売マンション・収益ビル・倉庫・工場・遊休地・相続物件など≫
TEL06-6360-9791




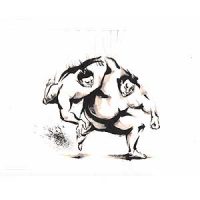 その銀行は日本のD銀行の台北支店だったので、売主はD銀行の本店に確認の電話をしました。
その銀行は日本のD銀行の台北支店だったので、売主はD銀行の本店に確認の電話をしました。 不動産の契約は
不動産の契約は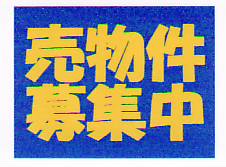

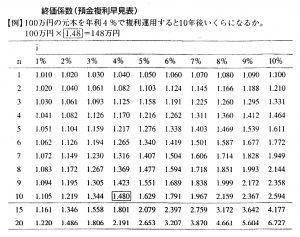
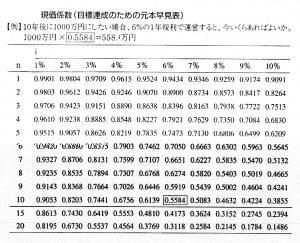
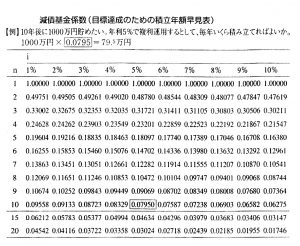
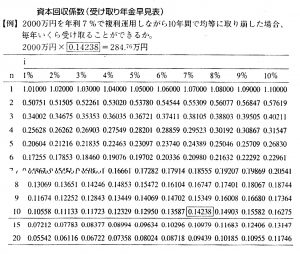
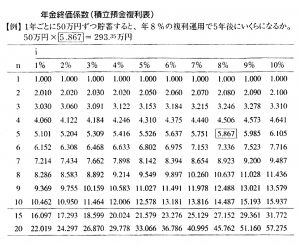
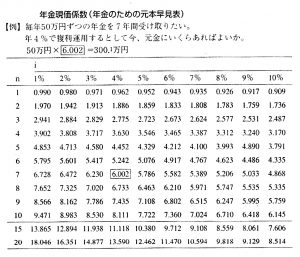


 。
。 一般の方からすれば、
一般の方からすれば、