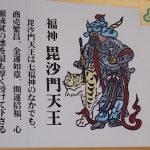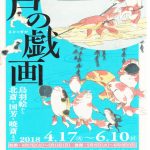不動産屋っていう仕事は、物件を見に行ったり、調査に出掛けたり、打ち合わせにお伺いしたりすることが日常的にあります。
いつも決まったところに行くというよりも、色々な処に出掛けることの多い仕事です。
プライベートで郊外へも行くこともありますので、チョコチョコと写真を撮って保存しております.
ここは、そんな超個人的なギャラリーです。
街の風景
ブログ
姫路名物のえきそば
- 姫路駅は1日に約51000人の人々が利用していて、駅から真正面に姫路城が見ることが出来ます。 姫路駅は日本初の「幕の内弁当」を販売したことで有名な駅です。
- 昭和24年に誕生したえきそばは、こんにゃく粉とそば粉を混ぜて作ったものが始まりと言われていますが、姫路駅で味わえる美味しい立ち食いそばとして知られています。
- 姫路名物えきそばは、和風だしに中華そばっていう感じで1日2000食売れるとか。店舗が電車形になったのは、2019年みたいですから、まだ新しいですね。
天王寺七坂めぐり

大阪天王寺七阪めぐり:上町台地の西側、天王寺区の谷町筋と松屋町筋の間に天王寺七坂と言われる坂があります。豊臣期に生玉社が現在地へ遷座し、徳川期に大坂市中の寺院を整理して寺町が造成されたこともあって、いずれの坂も沿道に寺社が多い。真田幸村ブームの際はパワースポットとなりました。
- 【愛染坂】
- 【天神坂】
- 【真言坂】
- 【逢坂】
- 【口縄坂】
- 【源聖寺坂】
- 【清水坂】
大阪五低山
大阪五低山(おおさかごていざん)とは大阪市内の五つの低い山のことで、大阪人特有の”いちびった”言葉遊びなのでしょうか。
「いちびる」って「ふざける」とか、「調子にのる」とかいう風な意味です。
本来、大阪市内には山は無いとされているので、五低山も古墳や人工的に土を盛ったものです。
仕事で物件を見に行ったりする後などに、こういう名所旧跡などに立ち寄ると少し旅行気分を味わえてホッとした気分になります!
- 大阪五低山【帝塚山】 大阪市住吉区帝塚山西二丁目 標高19.88メートル
- 大阪五低山【天保山】 大阪市港区築港三丁目 標高4.53メートル
- 大阪五低山【茶臼山】 大阪市天王寺区茶臼山町 標高26メートル
- 大阪五低山【聖天山 】 大阪市阿倍野区松虫通三丁目 標高14メートル
- 大阪五低山【御勝山】大阪市生野区勝山北 標高13.3メートル
//////////////////////
事業用不動産の売却・購入・買い替えなどのご相談はお気軽にご連絡お願い申し上げます。
≪一棟売マンション・収益ビル・倉庫・工場・遊休地・相続物件など≫

TEL06-6360-9791
南森町不動産の「会社案内」
南森町不動産の「お問い合わせ」
ギャラリー
- 【79人死亡 天六ガス爆発事故】 1970年、大阪で万国博覧会が開催して3週間後、地下鉄谷町線建設現場の天神橋六丁目でガス爆発がありました。 4月8日で事故から50年。 当時、中学生だった私も夕方のテレビで大騒ぎしていたのを覚えています。 国分寺公園には慰霊碑が建っています。 綺麗なお花が供えられていました。
- 【京都冬の風物詩】平成30年に新しくなった新南座の12月吉例顔見世興行の看板 江戸時代初期に起源する劇場で、同一の場所で今日まで興行を続けてきたという意味では、日本最古の劇場である。正式名称は京都四条南座、名称の由来は四条通の南側に位置しているため。
- 歌舞練場(かぶれんじょう)は京都市の祇園・先斗町などにある劇場。芸子さんや舞妓さんの歌・舞踊・楽器などの練習場です。
- 先斗町歌舞錬場は鴨川沿いにあり、1927年(昭和2年)の建築です。
- 三条大橋は1601年に徳川家康によって定められた東海道五十三次の西の起点。 弥次喜多像 江戸時代に出版された『東海道中膝栗毛』の主役である弥次郎兵衛と喜多八の像。 像の側にある撫で石を撫でると縁起がいいと言われている。
- 聖護院八ツ橋総本店(しょうごいんやつはしそうほんてん)は京阪四条駅前に本社を置く、京都の名物「八ツ橋」などを製造・販売する江戸時代からある和菓子販売の会社です。
- 難波の繁華街のど真ん中にあった精華小学校(1873年開校)が1995年に閉校し、2011年に大阪市の財政難により、建物を解体して売却しました。周辺の地上げなどもあった後に、今年(令和元年6月)に大手量販店エディオンのなんば本店として開業しました。
- 難波の新歌舞伎座跡地(大阪市中央区難波)の令和元年12月1日に開業する。デザインは隈研吾氏が担当、元の新歌舞伎座の面影を残し、客室150室のホテルです。 インバウンドに沸く大阪のシンボル的な建物になりそうです。
- 毎年数万枚の貨幣が張り付けられた「招福大まぐろ」は、西宮神社十日えびすの名物の一つとなっています。
- 西宮神社は 福の神として崇敬されている えびす様をおまつりする神社の総本社です。
- 十日えびすの準備は一月八日に卸売市場の若者の威勢のよい掛け声とともに奉納される大マグロで整います。
- 堀川戎神社は、大阪市北区にある。 大阪市内南部の今宮戎神社および兵庫県の西宮戎神社などと共に商売繁盛の神様として知られている
- 本殿は地車(だんじり)の形をしており、地車稲荷の通称で知られ、かつての榎の大木の根元には吉兵衛という老狸が住んでおり、毎夜、決まった時間に地車囃子の真似をしていたと伝えられる。本殿が地車型なのはそのためである。地車稲荷の神使は狐ではなく狸です。
- 江戸時代中ごろより祭礼が盛り上がり、 ミナミの今宮えびすとキタの堀川えびす が大阪の十日えびすを代表するようになる。 また今宮戎、西宮戎と並び、「三大戎」に数えられる。
- 戎さまは、左脇に鯛を右手に釣竿をもっておられます。その姿は、もともと漁業の守り神であり、海からの幸をもたらす神を象徴しています。
- 1月9・10・11日の三日間の祭礼で約100万人の参詣者があり、大変な賑わいをみせてくれます。
- 十日戎の笹は常に青々とした葉をつけているところに、「いのち」を常に甦らせている神秘性、その姿は神道の信仰そのも ので、神々のご神徳によって、日々「いのち」が甦り、生成発展している姿を象徴しています。
- 梅田のど真ん中に「歯」の神社があるのをご存じですか。
- 「歯」全般の神さまとして信仰されております。
- 入り口から楽しそうな戯画の始まりです。
- 2階から眺めて1階のホールにある写真を撮るのに絶好のパネルです!
- トイレに入ってビックリ!!レトロ調の男子トイレに思わずシャッターを・・
- 貫禄の大阪市率美術館の外観です。
- 江戸時代の「戯画」の特別展。動物を使ってこっけいな人物象を描いています。歌川国芳はじめ取っ付き易い絵だったせいか、沢山の人でにぎわっていました。
- チンチン電車の愛称で知られる阪堺電車は、恵比須町から堺のまちを走り抜けるまちの風物詩として明治44年の開業以来約100年間、庶民の足としても親しまれています。
- 桜宮橋(銀橋)は、大阪市の大川に架けられた国道1号の橋で北区天満橋1丁目と都島区中野町1丁目を結んでいる。国道1号の拡張および銀橋の補修工事のために、北側に新銀橋が建設された。新銀橋は安藤忠雄の設計。
- 大阪市福島区大開1丁目。大正7年 に「松下電気器具製作所」を創立した創業の地。 【道】自分には 自分に与えられた道がある 広い時もあるせまい時もある のぼりもあれば くだりもある 思案にあまる時もあろうしかし 心を定め希望をもって歩むならば 必ず道はひらけてく 深い喜びもそこから生まれてくる 松下幸之助
- 大阪天満宮の正門斜向いにある料亭「相生楼」の門前に『川端康成生誕之地』と記された石碑がある。、「伊豆の踊り子」「雪国」「古都」などの作品で知られる川端康成は、現在の北区天神橋1)で生まれた。康成の父で医師だった栄吉はこの地で開業していた。